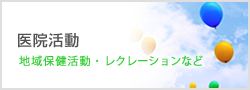ダウン症候群の患者さまの診療について2
こんにちは!小畑歯科医院、歯科医師の岡です。今回はダウン症候群の患者様について専門的な視点でお話させていただきます。

ダウン症候群は、21番染色体が3本ある「21トリソミー」によって生じる先天性の疾患です。我が国の患者数はおよそ5万人とされ、平均寿命は1950年代まで10歳以下でしたが、医療の発達により現在の平均寿命は約60歳代とされます。平均寿命が長いことを考慮すると、ダウン症候群の方の人口は増加傾向と考えられます。
次に、主な合併症(ダウン症候群が原因となって起こる別の病気)についてお話します。

ダウン症候群の方にみられる歯科的特徴についてお話します。
小顎(下顎が小さい)、高口蓋(うわあごが狭くて高い)、開咬・反対咬合(受け口や前歯がかみあわない)、舌突出(筋力の弱さから舌が前に出やすい)などがみられます。
歯の萌出遅延(通常より歯が生えるのが遅い)、歯の先天欠如(生まれつき歯がない)、矮小歯(小さい歯)、円錐歯(異常な形をした歯)などがみられます。
免疫機能の低下により、重度の歯周病になりやすく、年齢に比べて進行が速い傾向にあります。

口腔健康管理を行う上で配慮すべき事柄についてお話します。
心疾患への対応⇒感染性心内膜炎の予防のため、必要に応じて抗菌薬の事前投与を行います。
●知的能力障害の程度に応じた対応
・言語理解や表現に制限があることが多いため、簡潔で視覚的な説明(絵カードやジェスチャーを交えたコミュニケーション)が有効です。
・ご両親や支援者(施設の職員の方など)からの情報取集(普段のコミュニケーション方法、好きなことや苦手なこと)
●慣れるためのトレーニングが必要な場合が多い
・初診から徐々に慣れていくようにトレーニングを行います。(チェアーに寝る、ブラッシング、好きな味の歯磨剤をつける、器具に慣れる、触るなど)
・ルーティンを重視。毎回の手順が同じだと安心しやすいです。
●感覚過敏やこだわりがある場合
・音や光への配慮(治療機器の音を事前に聞いてもらう。照明を和らげる。)
・同じ器具や手順を使います。好きな音楽や安心できるものを持ってきていたたくのも有効です。
協力がどうしても得られない場合、鎮静法や全身麻酔下でのむし歯治療を選択せざるを得ない場合もあります。お医者様との連携も非常に大切です。
そうならないためにもトレーニングや予防処置(歯石取りやシーラント、フッ素塗布)などを幼少期から行い、口腔健康管理を行っていく必要があります。ご本人にはもちろん、歯ブラシ指導やフッ素の大切さなどの健康教育を、ご家族や施設の職員などの支援者に対しても、お願いすることが大切です。
住み慣れた地域で可能な限り自分らしい生活を継続していくためには、歯科関係者はもちろん多職種の方々とも連携して、ご本人とご家族を支援していく体制が望まれています。
♬――――――――――――――――――――♬
健康をサポートする和歌山市の歯医者さん・ウェルネス小畑歯科医院の日常や、歯科に関する情報を発信しています。
【一般歯科・歯周病治療・つまようじ法・障害者歯科・小児矯正】
ご予約はHPのウェブ予約ページ、またはお電話にて。
☎︎073-455-9874
投稿日:2025年7月22日 カテゴリー:ブログ